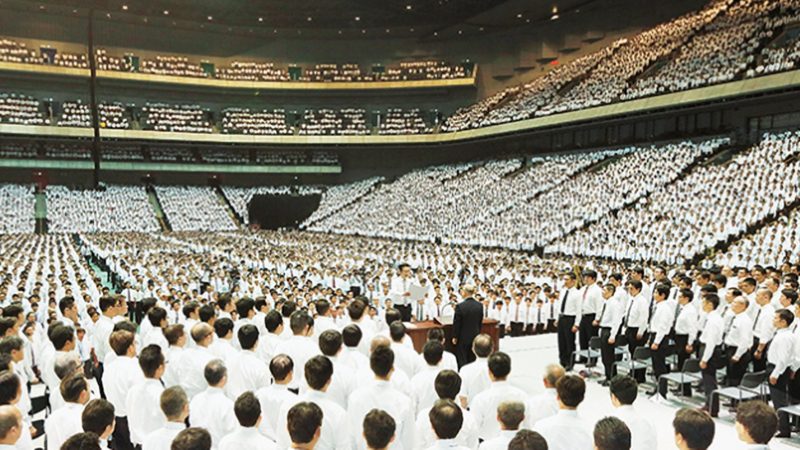未だに国立戒壇を否定する学会・宗門
これまでこのブログの記事をお読み頂いた方には、日蓮大聖人の御遺命である「本門の戒壇」とは、広宣流布の暁に、国家意志の公式表明を以て、富士山天生原に建立される国立戒壇であることが、よくよくご理解頂けたものと思います。
ところが、御遺命に背き、偽戒壇・正本堂を指して「御遺命の戒壇」と偽った学会・宗門(日蓮正宗)は、平成10年に正本堂が崩壊した後も、未だに国立戒壇を否定し、顕正会を怨嫉し続けています。
もし一分の信心あるならば、どうして大聖人の御遺命を平然と否定し続けることができるでしょうか。彼らには「信心がない」のです。
そこで、今回は、日蓮大聖人の御遺命に背く輩の邪難を取り上げ、その誤りを指摘していきたいと思います。
実はもう破折済みでした(笑)
早速、ネット上に溢れる夥しい数の「国立戒壇」に対する邪難に目を通してみました。すると、なんということでしょう!ほとんどが、浅井先生によってとっくの昔に破折されたものか、その焼き直しではないですか(笑)
具体的には、浅井先生が平成2年に著された「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」と題する書籍の中で、すでに完膚なきまでに破折し尽くされているのです。これを拝読すれば、ネット上に溢れる邪義も、「ああ、ここをごまかしているんだな」というのが一目でわかります。

有難いことに、最近ではAmazonでも購入できるようです。大聖人の御遺命の正義を知りたい方、ぜひご一読あれ!
これで終わりでも良いのですが、それではあまりに味も素っ気もないので(笑)、ここでは、最近、宗門(日蓮正宗)の輩が垂れ流している邪難をいくつか取り上げ、簡単に破折してみたいと思います。
「『国立戒壇』という言葉を使わなくなっただけ」の欺瞞を破す
「宗門は『国立戒壇』という言葉を使わなくなっただけ。『国立戒壇』は、もともと田中智学(邪宗の徒)が言い出した言葉だから、これを使わなくても問題ない」という主張です。
具体例を挙げてみましょう。
まず日蓮正宗本種寺(埼玉県川越市)の公式サイトです。
国立戒壇という言葉は、明治時代、邪宗・国柱会の田中智学が初めて言い出したものです。 それが当時の時代背景とマッチして、次第に国立戒壇の語が広く用いられるようになったので、 日蓮正宗においても、この語を自然に使用するようになったのです。
しかし、もともと国立戒壇は日蓮大聖人の教義ではなく、明治以前の日蓮正宗にはその言葉すら存在しなかった のですから、日蓮正宗第六十六世日達上人が「今後は、国立戒壇の語を用いない」 と決定されたことは全く問題の無いことです。
次に日蓮正宗妙通寺(愛知県名古屋市)の公式サイトです。
「国立戒壇」という言葉は、日蓮大聖人は一度も使われていません(御書の中には出てこない)。ですから現在、日蓮正宗では、その言葉を使用していません。
しかしだからといって「広布の精神」と熱烈な信行を捨てたわけではないのです。ただ、明治時代以降につくられた「国立戒壇」という言葉を、あえて使わなくなっただけのことなのです。
一見、もっともらしく見えますが、この主張には次の2つの欺瞞があります。
① 「田中智学」を引き合いに出すことで、あたかも「国立戒壇」という言葉が教義上不適切であるかのように思わせる印象操作をしている
② 宗門(日蓮正宗)は、御遺命の戒壇の内容(教義)をも改変したにもかかわらず、単に「国立戒壇」の名称を使用しなくなっただけと偽っている
以下、順番に見ていきましょう。
まず、①についてです。
確かに「国立戒壇」という名称を初めて使用したのは国柱会の田中智学です。しかし、田中は、冨士大石寺に伝わる御遺命の戒壇の義を盗み、それをあたかも自身発明のごとく世に喧伝したにすぎません。つまり、「国立戒壇」という名称は、本来、大石寺に伝わる御遺命の戒壇を指す名称なのです。
では、この名称は教義上不適切なのかといえば、答えは否です。
なぜなら、少なくとも3代にわたる先師上人(日享上人、日昇上人、日淳上人)が、戦後の日本国憲法下において、公の場で、御遺命の戒壇を指して「国立戒壇」と繰り返し呼称されていたからです。

「国立戒壇」を堅持された日淳上人
仮に「国立戒壇」という名称が教義上不適切なのであれば、これら英邁な先師上人が公の場で繰り返し使用されるはずがありません。
したがって、「国立戒壇」という名称は、教義上何ら不適切なものではありません。
むしろ、三大秘法抄の「王法仏法に冥じ・・・勅宣並びに御教書を申し下して」建立される戒壇を約言すれば、まさしく「国立戒壇」というべきでしょう。
次に②についてです。
宗門は、単に「国立戒壇」の名称を使用しなくなっただけではありません。その前提として、御遺命の戒壇の内容(教義)をも改変したのです。
にもかかわらず、教義改変の事実を隠し、「単に名称を使用しなくなっただけ」と偽っているのが、この欺瞞の本質です。
具体的に見てみましょう。
宗門は、偽戒壇・正本堂を指して、これを「御遺命の戒壇」と偽称しました。

一例を挙げれば、昭和42年、菅野慈雲宗会議員は、「正本堂建立は即ち事の戒壇であり、広宣流布を意味するものであります。この偉業こそ、宗門有史以来の念願であり、大聖人の御遺命であり、日興上人より代々の御法主上人の御祈念せられて来た重大なる念願であります」と発言しました(大日蓮昭和42年11月号)。
また、昭和43年には、細井日達も、「此の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり、王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」と発言しています(大白蓮華昭和43年1月号)。
そのような中、昭和45年3月に浅井先生が宗門諌暁を開始。細井日達を直諌された結果、さすがの日達も正本堂完成時を指して広宣流布達成とは言えなくなりました。
しかし、学会におもねる日達は、昭和47年4月28日、ついに「正本堂は御遺命の戒壇となるべき建物を前以て建てたものであり、広宣流布の暁にはそのまま『本門寺の戒壇』となる」旨の訓諭を出すに至ったのです。
そもそも御遺命の戒壇とは、先に書いたとおり、広宣流布の暁に、国家意志の公式表明を以て、富士山天生原に建立される国立戒壇ですから、かかる時・手続・場所の条件を満たさない正本堂が御遺命の戒壇に当たらないことは明らかです。
また、かかる条件が整っていないのに御遺命の戒壇となるべき建物を前もって立ててしまうことも、「勅宣並びに御教書を申し下して」の手続を無視し、「時を待つべきのみ」の御制戒に背くものです。
このように、宗門は昭和40年代において、偽戒壇・正本堂を正当化するために、七百年来叫び続けてきた国家的建立による御遺命の戒壇の内容(教義)を改変してしまったのです。だから御遺命違背というのです。
ちなみに、宗門が「国立戒壇」の名称を使用しないと決定したのは、教義改変の渦中にある昭和45年5月3日でした。これが池田大作の要請によるものであったことは、同年4月14日付の「阿部メモ」に明記されています。
このような経緯も、教義改変の事実も隠して、「単に『国立戒壇』の名称を使用しなくなっただけ」などと偽るのは、まさに恥知らずというほかありません。
「国家が管理したら戒壇の大御本尊を護れない」の欺瞞を破す
最近目にするようになったのが、「国立で戒壇を建立したら、戒壇の大御本尊を国家の手に委ねることになり、もし将来国の方針が変わったら大御本尊をお護りできなくなる。だから国立戒壇は絶対にあってはならない」という主張です。
ハッキリ言って、「はぁ?なに寝言言ってるんですか??」というレベルの恥論なのですが、なんと宗門末寺の公式サイトに堂々と掲載されているからオドロキです(笑)
再び具体例を挙げてみましょう。まず日蓮正宗本種寺(埼玉県川越市)の公式サイトです。
そもそも国立とは「国が設立し、管理をしていること」を意味します。
仮に国立で戒壇を建立すれば、そこに安置する本門戒壇の大御本尊を国家の手に委ねてしまうことになり、もし将来、国家の方針が変わったら、大御本尊を御護りすることができなくなってしまいます。
大御本尊護持という根本の信心に立てば、国立戒壇は絶対にあってはならないことなのです。
次に日蓮正宗妙通寺(愛知県名古屋市)の公式サイトです。
万一、「国立の本門戒壇堂」が天母山に完成したとして、また万一、そこに本門戒壇の大御本尊を御遷座したとして、その施設は誰が管理するのでしょうか? やはり「国立戒壇」ですから、運営や管理は日本政府に委ねることになるのではありませんか。
すると、その先もしも退転者が相次いで政治情勢が変わり、戦時下に国家神道を強制したような人たちが政権を担うような時代に逆もどりした場合、はたして大御本尊は、どのように扱われるようになるのか不安ではありませんか?
浅井会長自身、国家や政治は、時代や状況が変われば、人間の都合によってコロコロ変わるのが常であると指摘しています。そういった変節した政治家や役人たちに「国立だから」といって、大御本尊を託すことなど到底出来ようはずもありません。そうした意味から、むしろ将来の戒壇堂建立は、ぜったいに「国立」であってはならないとさえ言えるのです。
例によって、この主張にも次の2つの欺瞞があります。
① 顕正会が主張していない内容(大御本尊を国家の手に委ねる)を捏造し、その捏造した内容を批判することで、あたかも顕正会の主張を破折したかのように見せかけている
② 「戒壇建立の必要手続」の問題と、「建立後の大御本尊護持」の問題を混同している
では、順番に見ていきましょう。
まず、①についてですが、そもそも顕正会は、本門戒壇の大御本尊を「国家の手に委ねてしまう」とか、「政治家や役人たちに・・・大御本尊を託す」などと主張したことはありません。
これは顕正会が主張していない内容を勝手に「捏造」したものです。
したがって、顕正会がそのような主張をしていることを前提とするこの邪難は、その前提を欠いていて的外れというほかありません。
次に②について。
浅井先生は、「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」において、「では、国立戒壇の『国立』たるゆえんはどこにあるのかといえば、実に『勅宣並びに御教書』すなわち国家意志の表明にある。かくて始めて仏国実現が叶うのである」と明快に仰せです(「御書には国立戒壇の語はない」に対する破折部分)。
つまり、「戒壇建立の必要手続」として国家意志の表明を必要とするゆえに、「国立戒壇」というのです。
このことは、「国立戒壇」の名称を使用された歴代先師上人も同様であり、およそ「戒壇の御本尊を政治家や役人に託す」などという意味で用いた方は一人もおられません。
そして、戒壇建立の手続として「国家意志の表明」が必要だからといって、その建立後に、本門戒壇の大御本尊を政治家や役人たちの手に委ねることにはなりません。大御本尊を護持されるは、あくまで血脈付法の貫首上人だからです。
しかるに宗門側は、「仮に国立で戒壇を建立すれば、そこに安置する本門戒壇の大御本尊を国家の手に委ねてしまうことにな(る)」(本種寺)などと、全く「的外れ」な批判をしています。これは「戒壇建立の必要手続」の問題と、「建立後の大御本尊護持」問題という、本来全く別個の問題を「混同」しているからです。
このこと、もし意図的にやっているとしたらお粗末、知らずにやっているとしたら無能と言わざるを得ません。
本種寺のサイトなどは、「このように顕正会が主張する国立戒壇論はデタラメであり、日蓮大聖人の教えなどではありません」などと嘯いていますが、およそ顕正会が主張してもいない「トンデモ論」を自ら「捏造」してはしゃいでいるのですから、どちらが「デタラメ」であるかは一目瞭然です。
大石寺発行「諸宗破折ガイド」を破す
さて、次は宗門(日蓮正宗)が発行している書籍を見てみましょう。
どうやら宗門は、平成15年3月に「諸宗破折ガイド」なる書籍を発行し、その中で顕正会のことを口を極めて中傷しているようなのです。
一読してみたところ、ああ無慚・・・。未だに大聖人の御遺命たる国立戒壇を否定し、稚拙な愚論を展開しているではないですか。
そこで、この「諸宗破折ガイド」における国立戒壇に対する邪難を破折し、いまの宗門のレベルがどの程度であるかを検証してみたいと思います。
「『国立戒壇』は田中智学が言い出した言葉。法主が『今後は使わない』と言っている」の欺瞞
「あれっ、これさっきやらなかったっけ?」と思われたそこのあなた。ええ、そうなんです。どうやら宗門末寺の公式サイトは、この「諸宗破折ガイド」をタネ本にしているようですね(笑)
まず、このように書かれています。
「国立戒壇」という名称は御書にはない。この名称をはじめて使用したのは、明治時代の立正安国会(後の国柱会)の創始者であった田中智学である。智学は国粋主義者で、当時の時代風潮に乗って、国立戒壇の名称を用いた。この頃、日蓮門下でも富士戒壇論が盛んになり、本宗においても法論等のなかで便宜上使ったこともあったが、国立戒壇という語句自体を伝統教義として扱ったり、宗門の公式見解として使用したことはない。
これは先の「『国立戒壇』という言葉を使わなくなっただけ」の欺瞞のところで破折したとおりです。
英邁な先師上人が公の場で用いられた「国立戒壇」の呼称について、「田中智学」を引き合いに出すことによって、あたかも教義上不適切な言葉であるかのように思わせる印象操作をしているのです。
ただし、ここで着目すべきは、「本宗においても法論等のなかで便宜上使ったこともあったが、国立戒壇という語句自体を伝統教義として扱ったり、宗門の公式見解として使用したことはない」という部分です。
これは真っ赤なウソですね。
なぜなら、歴代先師上人は、「国立戒壇」という言葉を、単に「法論等のなかで便宜上使った」だけではなく、まさしく大聖人以来の御遺命の戒壇をあらわす言葉として公の場で使用されていたからです。
文証を引きます。
第六十四世・日昇上人は、奉安殿慶讃文において、「国立戒壇の建立を待ちて六百七十余年今日に至れり。国立戒壇こそ本宗の宿願なり」と仰せられています。
これは昭和30年、「奉安殿」と名づけられた新御宝蔵が建設された際の慶讃文ですから、当然、「法論等のなかで便宜上使った」ものではありません。公の場において、「本宗の宿願」を表現するお言葉として「国立戒壇」を用いておられます。
また、第六十五世・日淳上人は、元朝勤行に事寄せて、「この元朝勤行とても、宗勢が発展した今日、思いつきで執行されたというものでは勿論なく、二祖日興上人が宗祖大聖人の御遺命を奉じて国立戒壇を念願されての広宣流布祈願の勤行を、伝えたものであります」(大日蓮34年1月号)と仰せられています。
これも、元朝勤行におけるお言葉ですから、「法論等のなかで便宜上使った」ものではありません。
やはり、公の場において、二祖日興上人が奉じ奉った「宗祖大聖人の御遺命」を表現するお言葉として「国立戒壇」を用いておられるのです。
これらはあくまで一例ですが、このように歴代先師上人は、「国立戒壇」という言葉を、単に「法論等のなかで便宜上使った」だけではなく、まさしく大聖人以来の御遺命の戒壇をあらわす言葉として公の場で使用されていたのです。
したがって、「諸宗破折ガイド」の先の記述は真っ赤なウソと言わざるを得ません。
かえって、「田中智学」を持ち出して「国立戒壇」の名称を殊更に軽侮することは、これを「御遺命の戒壇をあらわす言葉」として公の場で用いられた歴代先師上人に対する侮辱とも言い得るでしょう。
続いて、「諸宗破折ガイド」は、次のように論を進めます。まず、
ここで最も大切なことは、宗祖大聖人の血脈を継承される時の法主上人がその時代性を鑑みて、どのように指南されるかということであって、この指南に従うことが日蓮正宗の信仰の在り方である。
と前置きした上で、細井日達が国立戒壇の名称を使用しない旨を決定した事実を挙げ、
こうした経緯を弁えずに、顕正会が「近代の御法主上人の仰せに国立戒壇の語があるのに、現在の大石寺は国立戒壇を捨てた」などと喚くのは、まったくの戯言にすぎない。
と結んでいます。
要するに、御遺命の戒壇について「国立戒壇」の語を用いるか否かは、時の法主の指南に従うべきであるところ、すでに細井日達が「国立戒壇」の名称を使用しないと指南しているのであるから、これに反して顕正会が「現在の大石寺は国立戒壇を捨てた」と主張するのは戯言だ、という論法です。
しかし、すでにお気づきの方もいるかと思いますが、実はこれも「『国立戒壇』という言葉を使わなくなっただけ」の欺瞞のところで破折済みなのです。
つまり、顕正会は、宗門が「国立戒壇」の名称を使用しなくなったこと自体を指して「御遺命違背」と言っているのではなく、偽戒壇・正本堂を正当化するために、七百年来叫び続けてきた国家的建立による御遺命の戒壇の内容(教義)を改変してしまったことを「御遺命違背」と言っているのです。
要するに、ガイドの反論は、全くズレているのです。まさに「まったくの戯言」というほかありません。
ところで、「諸宗破折ガイド」は、宗門の教義改変について一言も言及していません。
あれほど偽戒壇・正本堂を「御遺命の戒壇になる建物だ」と大々的に公言していたにもかかわらず、その是非について何ら釈明していないのです。
これは正本堂がわずか26年で崩壊し、御遺命の戒壇ではなかったことが露顕したために、戒壇の意義に関する宗門見解が間違っていたことが証明されてしまったからです。
要するに、宗門が御遺命を曲げた事実については釈明の余地がないのです。
そこで、「単に名称を使用しなくなっただけ」とか、「どんな名称を使うかは法主が決めること」などと、ことさら「名称」だけに焦点を絞る姑息な論点ずらしに走るわけです。哀れですね(笑)
事の戒壇建立の時期・手続・場所について議論してはいけない??
次に「諸宗破折ガイド」は、御遺命の戒壇が建立されるべき時・手続・場所について、次のように論じています。
まず顕正会の主張を取り上げていわく、
顕正会は『一期弘法抄』の、「・・・」また『三大秘法抄』の、「・・・」等の御書を論拠として、事の戒壇建立に関する時期や、手続、場所などを勝手に主張している。
(注、「・・・」部分は御文を省略)
顕正会では戒壇建立の時期について、日本国の広宣流布のときとし、その広宣流布を、天皇をはじめとする上下万民が三大秘法を信じた時と規定している。また手続について、「勅宣並びに御教書」とあることなどから、国権の最高機関である国会の議決、またこの議決に基づく内閣の決定がそれに当たるとし、さらには場所について、天母山(現在は天母原に変更)と指定している。
やや不正確ではありますが、顕正会が「一期弘法抄」ならびに「三大秘法抄」等の「御書を論拠として」、御遺命の戒壇の時・手続・場所について概ね如上の主張をしているのは事実です。
念のため、正確な内容を記せば、「手続」は国家意志の表明、「場所」は富士山南麓の天生原(大石寺の東方4キロに位置する勝地)です。
宗門ですら、顕正会の主張が「御書を論拠として」いると認めているのは滑稽ですね(笑)
ところが、「諸宗破折ガイド」は、この「御書を論拠」とする顕正会を次のように中傷しているのです。
しかし、将来、国情などがどのように変化していくのかわからない現時において、未来の広宣流布達成における戒壇建立の形態を云々することは、不毛の論である。それは時の法主上人が血脈所持のうえから指南されるもので、それ以外の者が議論すべきことではない。大聖人の御遺命を、血脈不相伝の輩が勝手な解釈を加えて論ずることは、大謗法と断じるものである。
この主張の欺瞞・誤りは次の3つです。
① 顕正会は、宗門の「過去」及び「現在」における教義改変を指して御遺命違背と主張しているのに、「将来」のことについて論じるのは「不毛の論」と逃げ、論点をすり替えている
② 戒壇の意義につき、「法主以外の者が議論すべきことではない」として、宗門の教義改変・御遺命違背に対する指摘をかわそうとしている
③ 御書及び歴代先師上人のご指南に基づく顕正会の主張を「勝手な解釈」と中傷している
では、順に見ていきましょう。
まず①についてです。
顕正会は、宗門が偽戒壇・正本堂を正当化するために七百年来叫び続けてきた御遺命の戒壇の内容(教義)を改変したこと、そして、正本堂崩壊後も未だに改変し続けていることを指して「御遺命違背」と諌めています。
つまり、宗門の「過去」及び「現在」における教義改変を問題としているのです。
しかるに「諸宗破折ガイド」は、この「過去」及び「現在」における教義改変という重大な御遺命違背についてはダンマリを決め込みつつ、「将来、国情などがどのように変化していくのかわからない現時において、未来の広宣流布達成における戒壇建立の形態を云々することは、不毛の論」などと、話を「将来どうするか」の議論にすり替えているのです。
これも、要するに過去・現在における御遺命違背(教義改変)について反論不能ということです。
次に②について。
宗門は、過去の御遺命違背の事実を指摘されるのがよほど痛いようです。それもそのはず、
「此の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり、王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」(大白蓮華201号)
などと、今から見れば赤面モノのデタラメ極まる説法を、細井日達みずからしていたのですから。
だから、戒壇の意義につき、「それは時の法主上人が血脈所持のうえから指南されるもの」「それ以外の者が議論すべきことではない」などと逃げているのです。
要するに、「そ、そこはさぁ、イタイところなんだからさぁ、それ以上突かないでくれよぉ~」と言っているわけです(笑)
しかし、そもそも御遺命の戒壇について、「時の法主」以外が口にしてはいけないという道理・文証はありません。
現に宗門坊主らも正本堂を指して、
「本門寺の戒壇」(大村寿顕)
「御遺命遊ばされた・・・最も重要な本門戒壇堂」(佐藤慈英)
「宗祖日蓮大聖人の御遺命」(椎名法英)
「事の戒壇」「広宣流布を意味するもの」「大聖人の御遺命」(菅野慈雲)
などと囀っていたわけです。
自ら御遺命違背の邪義を撒き散らしておきながら、その誤りを指摘されるや、「法主以外の者が議論すべきことではない」などと道理も文証もない口実で逃げを打つ宗門坊主らの姿は、もはや「惨め」の一言です。
最後に③についてです。
「諸宗破折ガイド」は、顕正会の主張を挙げ、「大聖人の御遺命を、血脈不相伝の輩が勝手な解釈を加えて論ずることは、大謗法と断じるものである」などとハリキッテいます。
しかし、「諸宗破折ガイド」が取り上げる顕正会の主張、すなわち戒壇建立の時・手続・場所の内容は、顕正会の「勝手な解釈」ではありません。大聖人の御金言及び歴代先師上人のご指南に基づくものです。
具体的に見ていきましょう。
戒壇建立の「時」について
「諸宗破折ガイド」は、顕正会の主張について、「日本国の広宣流布のとき」、具体的には「天皇をはじめとする上下万民が三大秘法を信じた時」と紹介しています。果たしてこれは顕正会の「勝手な解釈」なのでしょうか。
二祖日興上人は、御遺命の戒壇につき、「広宣流布の時至り、国主此の法門を用いらるるの時、必ず富士山に立てらるべきなり」と仰せられています(富士一跡門徒存知事)。
第三十一世・日因上人は、「国主此の法を持ち広宣流布の御願成就の時、戒壇堂を建立して本門の御本尊を安置すること、御遺状の面に分明なり」と仰せです。
では、その「広宣流布の時」とはいかなる時かといえば、
第五十六世・日応上人は、「上一人より下万民に至るまで此の三大秘法を持ち奉る時節あり、これを事の広宣流布という」と仰せられています(御宝蔵説法本)。
つまり、歴代先師上人は、戒壇建立の「時」について、「広宣流布の時」、具体的には「上一人より下万民に至るまで此の三大秘法を持ち奉る時節」とご指南くだされているのです。
戒壇建立の「時」についての顕正会の主張(「日本国の広宣流布のとき」「天皇をはじめとする上下万民が三大秘法を信じた時」)が、歴代先師上人のご指南に基づく正義であることは明らかです。
戒壇建立の「手続」について
顕正会は、「勅宣並びに御教書を申し下して」の御金言に基づき、国家意志の表明を戒壇建立の必要手続として主張しています。
では、これは顕正会の「勝手な解釈」なのでしょうか。歴代先師上人は、御遺命の戒壇を「国家と無関係に建てよ」と仰せになっているのでしょうか。
そもそも三大秘法抄には、大聖人御自ら「勅宣並びに御教書を申し下して」との手続を明確に定められています。この厳重の御定めをどうして無視し得るでしょうか。
されば、歴代先師上人は一糸乱れず国家的な建立をご指南くだされています。
第四十八世・日量上人は、「事の戒壇とは、正しく広宣流布の時至って勅宣・御教書を申し下して戒壇建立の時を、事の戒壇というなり」(本因妙得意抄)。
第五十六世・日応上人は、「上一人より下万民に至るまで此の三大秘法を持ち奉る時節あり、これを事の広宣流布という。その時、天皇陛下より勅宣を賜り、富士山の麓に天生ヶ原と申す曠々たる勝地あり、ここに本門戒壇堂建立あって・・・」(御宝蔵説法本)。
第五十九世・日享上人は、「この戒壇堂について、事相にあらわるる戒壇堂と、義理の上で戒壇とも思えるの二つがある。事相の堂は将来一天広布の時に、勅命で富士山下に建ち、上は皇帝より下は万民にいたるまで授戒すべき所である」(正宗綱要)、「この戒壇に事・義の二あり。国立戒壇は事なり、是れ未来一天広布の時の勅命によるべきがゆえに」(日蓮各教団の概観)。
第六十世・日開上人は、「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜り、本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし」。
第六十五世・日淳上人は、「大聖人は、広く此の妙法が受持されまして国家的に戒壇が建立せられる。その戒壇を本門戒壇と仰せられましたことは、三大秘法抄によって明白であります」(日蓮大聖人の教義)。
このように歴代先師上人もまた、大聖人が定められた「勅宣並びに御教書を申し下して」のお定めに従い、国家意志の表明に基づく国家的建立をご指南くだされています。
とりわけ日淳上人は、「国家的に戒壇が建立せられる」ことは「三大秘法抄によって明白」とまで仰せられています。一方、「国家と無関係に建てよ」というご指南は一つもありません。
ここでも、顕正会の主張が、御金言及び歴代先師上人のご指南に基づく正義であることは明らかです。
戒壇建立の「場所」について
顕正会は、戒壇建立の「場所」について、富士山南麓の天生原と主張しています。これも歴代先師上人の伝承に基づくものです。
文証を引きます。
第二十六世・日寛上人は、「事の戒壇とは、即ち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり。御相承を引いて云く・・・」(報恩抄文段)。
第三十七世・日琫上人は、「仏の金言空しからずんば、時至り天子・将軍も御帰依これ有り。此の時においては富士山の麓・天生原に戒壇堂造立あって・・・」(御宝蔵説法本)。
第四十八世・日量上人は、「(富士一跡門徒存知事の御文について)『本門寺に掛け奉るべし』とは、事の広布の時、天母原に掛け奉るべし」(本因妙得意抄)。
第五十六世・日応上人は、「上一人より下万民に至るまで此の三大秘法を持ち奉る時節あり、これを事の広宣流布という。その時、天皇陛下より勅宣を賜り、富士山の麓に天生ヶ原と申す曠々たる勝地あり、ここに本門戒壇堂建立あって・・・」(御宝蔵説法本)。
これらのご指南を拝すれば、顕正会の主張が「勝手な解釈」などではないことは一目瞭然です。
いかがでしょうか。大聖人の御金言及び歴代先師上人のご指南に照らせば、まさしく御遺命の戒壇とは、広宣流布の暁に、国家意志の公式表明を手続として、富士山天生原に建立される国立戒壇であることは、天日のごとく明らかです。
かかる正論を指して「勝手な解釈」などと中傷することは、むしろ大聖人及び歴代先師上人に対する許されざる背叛というべきです。
かえって、宗門は、御遺命の戒壇について、いかなる「解釈」をしていたのでしょうか。
これまで見てきたとおり、細井日達はじめ宗門坊主らは、偽戒壇・正本堂を指して「御遺命の戒壇」と大々的に公言していました。
つまり、未だ「広宣流布」が達成していないにもかかわらず、「勅宣並びに御教書を申し下して」の御定めを無視して、国家と無関係に宗門だけで建てた偽戒壇・正本堂を「御遺命の戒壇」に当たると「解釈」していたのです。
これは先に見た大聖人の御金言及び歴代先師のご指南からすれば、全くの己義、デタラメと言わざるを得ません。これこそ御遺命に背く「勝手な解釈」といい、「大謗法」というのです。
戒壇の御本尊在すところはそのまま「事の戒壇」??
続いて「諸宗破折ガイド」は、「事の戒壇」の定義について、次のような誑惑をかまえています。
「日蓮正宗においては、古来、本門戒壇の大御本尊在すところがそのまま本門の事の戒壇とし、そのうえで、将来に広宣流布が達成された暁に、信仰の根源の霊場として戒壇堂が建立されるとするのである。これが御遺命の『本門寺の戒壇』である」、「このように宗門における『事の戒壇』義は、終始一貫しており、なんら疑義を挟む余地はない」
つまり、「宗門では、古来より、本門戒壇の大御本尊ましますところがそのまま『事の戒壇』であり、この義は終始一貫している」と主張しているわけです。
しかし、第二十六世・日寛上人は、「未だ時至らざる故に、直ちに事の戒壇これ無し」(寿量品談義)として、広布以前に「事の戒壇」は無いことを明確に仰せられています。
では、「事の戒壇」とは如何なるものかといえば、日寛上人は、
「事の戒壇とは、即ち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり。御相承を引いて云く『日蓮一期の弘法、乃至、国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり』と云々」(報恩抄文段)とご指南されています。
つまり、「事の戒壇」とは、広布の暁に建てられる御遺命の戒壇をいうのです。
ゆえに第六十五世・日淳上人は、「蓮祖は国立戒壇を本願とせられ、これを事の戒壇と称せられた」(富士一跡門徒存知事の文に就いて)として、「事の戒壇」とは「国立戒壇」であると端的にご指南くだされています。
だからこそ、御遺命に背いた第六十六世・細井日達も、登座直後には、「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は広宣流布の時の国立の戒壇であります」(大日蓮36年5月号)と明言していたのです。
このように「事の戒壇」とは広布の暁に建てられる御遺命の戒壇であることは、文証分明、一点の疑義もありません。
ところが宗門は、昭和45年の顕正会の諌暁以降、突如としてこの定義を変更し、「本門戒壇の大御本尊在すところがそのまま本門の事の戒壇」などと主張するようになりました。
まさに宗門における「事の戒壇」の義は、「終始一貫」などとは言うも愚か、昭和45年の御遺命違背を機として全く別物に改変されてしまったのです。
では、なぜ宗門が「事の戒壇」の定義を改変したかといえば、偽戒壇・正本堂の誑惑を助けるためです。
つまり、定義改変によって「正本堂も『事の戒壇』に当たる」とすることで、あたかも正本堂が御遺命の戒壇であるかのように錯覚させようとしたのです。
そのため、本来であれば、平成10年に偽戒壇・正本堂が崩壊し、御遺命の戒壇でないことが露顕した以上、宗門は深い懺悔をもってこの定義改変を正し、伝統法義に立ち返るべきだったのです。
しかるに宗門は、偽戒壇・正本堂が崩壊した後も、定義改変を改めず、「本門戒壇の大御本尊在すところがそのまま本門の事の戒壇」「宗門における『事の戒壇』義は、終始一貫」などと嘯いていたのです。まさに厚顔無恥、無慚無愧というほかありません。
ちなみに、「諸宗破折ガイド」は、改変後の定義を正当化するために、これを裏付ける文証として次のものを挙げています。
①日寛上人「依義判文抄」
②日相上人聞書
③日開上人・御宝蔵説法本
④細井日達の説法
⑤日蓮正宗要義
しかし、まず④⑤は昭和45年の定義改変後のものですから、それ以前の大石寺の伝統法義を証明するものではありません。
また、②③のたばかりは、平成2年の「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」の中で完膚なきまでに破折されています(「四 『事の戒壇』の定義変更による誑惑」)。このような破折済みの論法を未だに繰り返しているとは、よほど無知か無恥なのでしょう(笑)
そこで、残った①について少しコメントすれば、これは「事の戒壇」の文証ではありません。
①は、依義判文抄の「一大秘法とは即ち本門の本尊なり。此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し」の御文ですが(注、下線は筆者)、これは「本門の戒壇」についての仰せであって、「事の戒壇」の定義を示されたものではないからです。
「本門の戒壇」に「事」と「義」があり、それぞれ別のものを指すことは本宗の常識です。
ガイドが①の文を引いているのは、「義の戒壇」を含む概念である「本門の戒壇」と、「義の戒壇」を含まない(峻別される)概念である「事の戒壇」、この2つを混同させることにより、あたかも戒壇の御本尊ましますところが常に「事の戒壇」に当たるかのように誤読させようとしているものと思われます。要するに、ペテンということです。
※ちなみに宗門は最近、「事の戒壇」の定義をこっそり元に戻しました!
日蓮正宗公式サイト(関連項目・正しい本尊とは)には、次のような記載があります。
「事の戒壇」とは、宗祖日蓮大聖人が、「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり」(新編1675頁)と仰せの、御遺命の本門寺の戒壇堂です。
もちろん、これは平成15年の「諸宗破折ガイド」の見解と全く相反するものです。
しかし、何より重要なことは、これが顕正会の主張と全く同じであるということです。
つまり、宗門は、「事の戒壇」の定義について、宗門が間違っており、顕正会の方が正しかったことを認めたということです。
「諸宗破折ガイド」などは、顕正会への誹謗に躍起になるあまり、この「事の戒壇」の正義に対し、「そこに不相伝の輩の短絡的な考え違いがある」「このように宗門における『事の戒壇』義は、終始一貫しており、なんら疑義を差し挟む余地はない。顕正会浅井の基本的な誤りは、大聖人の御書の意を自分勝手に判断するところにあるのであり、これは師弟子の道を違える謗法である」などと貶めています。
自らも正論と認めるに至った歴代先師の正義に対し、あろうことか、「不相伝の輩の短絡的な考え違い」、「大聖人の御書の意を自分勝手に判断する(もの)」などと口を極めて中傷していたのです。
これがコロコロと変節を繰り返す無道心の宗門の実態です。まさに「師弟子の道を違える謗法」と断じざるを得ません。
最後に、「諸宗破折ガイド」では、御遺命の戒壇を建立すべき地が「天生原」であることを否定する邪難を書いていますが、これは「戒壇建立の「場所」について」の部分で破折済みのため、ここでは割愛します。
終わりに
いかがだったでしょうか。
宗門末寺の公式サイトはもちろん、宗門が発行している「諸宗破折ガイド」なる本も、所詮、この程度のレベルなのです。こんな稚拙な邪義に誑かされている法華講員が哀れでなりません。
そもそも国立戒壇建立の御遺命は、顕正会の己義ではありません。昭和30年代まで、学会も宗門も一丸となってその実現を目指してきた大聖人唯一の御遺命です。
ゆえに、登座直後の細井日達は、「富士山に国立戒壇を建設せんとするのが日蓮正宗の使命である」(大白蓮華35年1月号)といい、池田大作もまた、「国立戒壇の建立こそ、悠遠六百七十有余年来の日蓮正宗の宿願であり、また創価学会の唯一の大目的なのであります」(大白蓮華五十九号)と述べていたのです。
しかるに広布前夜、第六天の魔王のたばかりにより、学会・宗門ともにこの御遺命をなげうち、偽戒壇・正本堂を指して「御遺命の戒壇」と偽称したのです。
その現罰を見れば、池田大作は2010年以降「生ける屍」となり、細井日達もまた臨終思うようにならず、「今まで見たこともないほどドス黒く、阿鼻獄を恐れ叫んでいるかのような相」を現じたのです(葬儀に参列した縁戚の話。顕正新聞平成30年10月5日号)。
「一切は現証には如かず。・・・実に正法の行者是くの如くに有るべく候や」(教行証御書)の御金言の、なんと重いことでしょうか。
日興上人は遺戒置文に、「時の貫首たりと雖も仏法に相違して己義を構えば、之を用うべからざる事」と仰せられています。また、その末文にいわく、「此の内一箇条に於ても犯す者は日興が末流に有るべからず」と。
されば、たとえ時の貫首の言葉であっても、御遺命に背く己義を用いてはならないのです。これを諫めず、これに従う者は、すでに日興上人の末流ではありません。
そこに、御遺命を守り奉った顕正会だけが、大聖人の御意に適い、また、「冨士大石寺」を冠する資格を有する所以があるのです。
このブログをご覧になった心ある学会員・法華講員の方々が、一日も早く御遺命の正義に目覚め、ともに広宣流布・国立戒壇建立に戦う同志となることを念願してやみません。